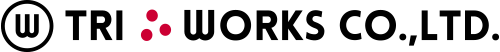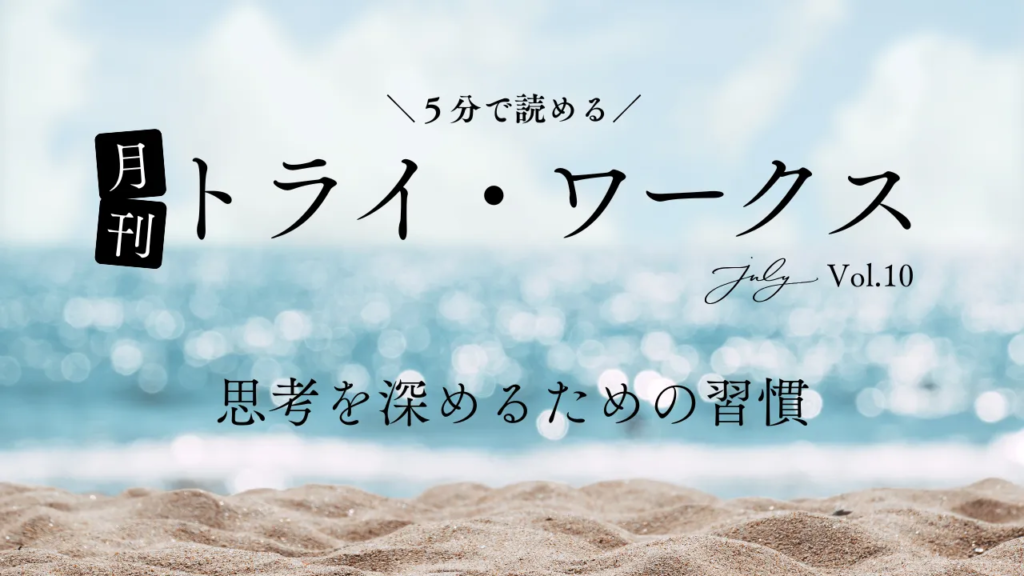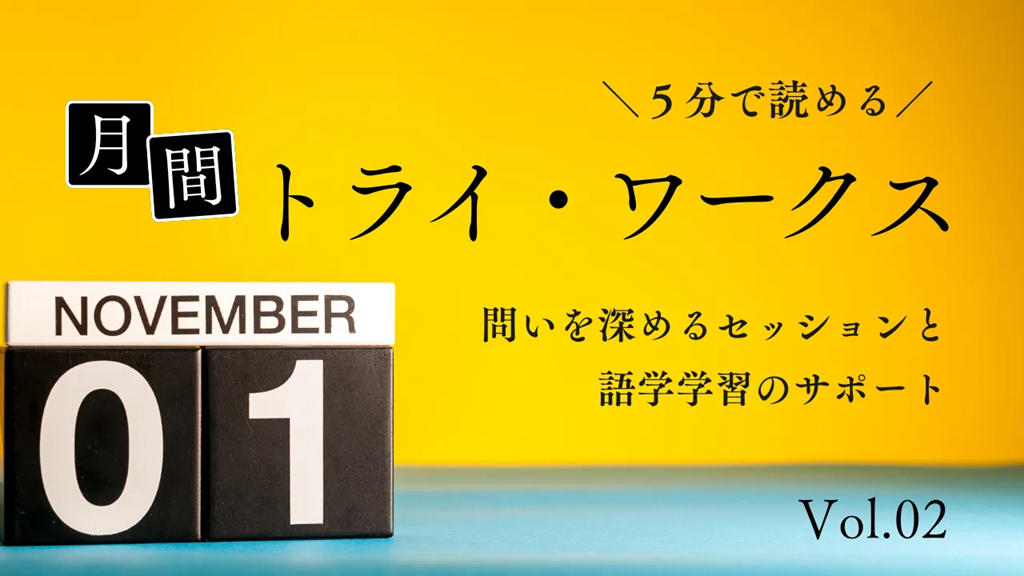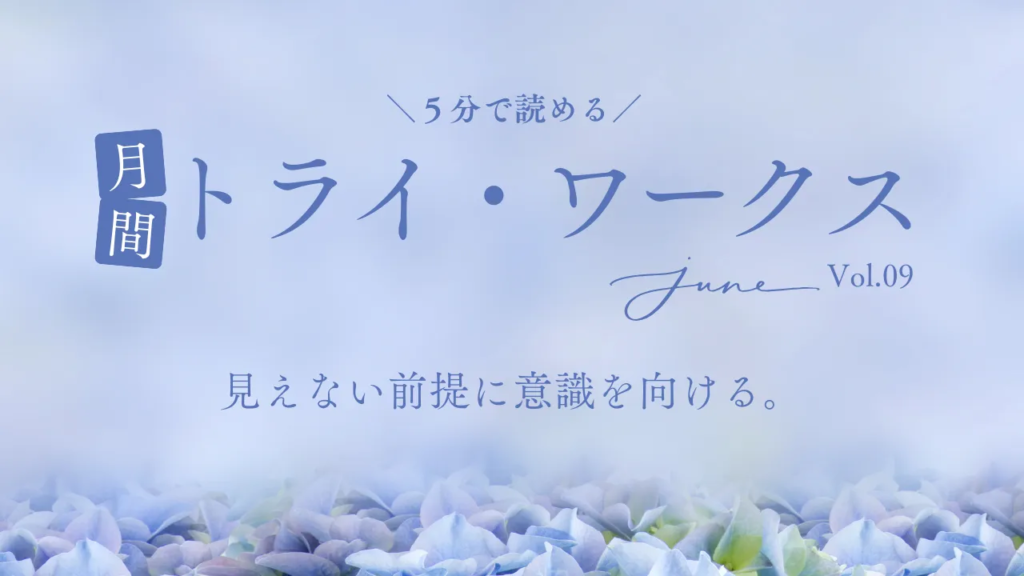梅雨明けして、いよいよ夏本番ですね!
2025年も半分終わりましたね。
いよいよ七夕会も来週!世の中も社内も、色んな出来事がありましたが、みんなで元気に会えることを楽しみにしています。さて、7月もスタート!
人工知能の時代に問われる“考える力”
昨今のAIの進化は目覚ましいですね。
かれこれ半世紀生きてきて、ここ数年であっという間に開発領域で実用可能なレベルになってきている。
人工知能の進化によってなくなる仕事もあると言われていますが、「何を解決するのか、どうやってやるべきか」という課題設定や要件定義は、暫くの間、少なくとも5年ぐらいは人がやることになると思うんです。
だからこそ、「問題」を感じる力、インパクトの大きな「課題」を見つける力を磨き続けたいものですね。
顕在化した問題の解決はしてくれるけど、前例のない(AIが学習していない)ことや、0から1を生み出すことは、「考える力」を使う。どれだけ知識量が多くても、実際に体験したこと、経験からしか導き出せないことはまだまだあって、こうじゃないか、ああじゃないかと仮説立てたり想像することによって身に付く後天的な部分も多い。
だからこそ、情報を鵜呑みにするだけじゃなくて、誰がどんな意図で発信してるのか?背景は?など、自分なりの視点で推察することが、思考力というスキルを高めると意識したいですね。
“なぜ?”のクセがつくと、世界は面白くなる
自宅にロボット掃除機を導入しました。
出始めから比べると音も静かで、水拭きまでしてくれて家の様子をカメラで見たり、話しかけたりできる高性能ぶり。
これだけロボット掃除機が普及する中、最初にルンバを発売したiRobotは経営不振。自前主義で意思決定や市場対応の遅さが要因だとされているそうです。マーケットを作った先駆者でも、市場が広がれば競合が増えて、製品も多様化していく。そもそも、模倣しやすい技術だったのかもしれません。
一方で、吸引力が強い掃除機で打ち出したダイソンは、自分たちの強みである風をコントロールする技術を活かして、ドライヤーやサーキュレーターでヒット商品を開発。製品に共通する「静かでパワフルなモーター」を応用して、ヘッドホンまで発売。B2Cで大きな市場へ食い込む傍ら、商業施設のトイレに設置されているハンドドライヤーでB2Bにも進出しています。何が命運を分けたのか?
これはロボット掃除機の購入をきっかけとした一つの話題でしたが、日常的な変化に目を向け、一見バラバラで関連性のない要素をつなぎ合わせたり、調べたりして推察すること。答えのない問いだとしても、思考する。この繰り返しで、考える力や着眼点が磨かれていくのかもしれません。
最近考えた出来事があったら、ぜひ聞かせてください。
事象を観察し、違和感に気付き、思考を深めること。
新聞の見出しや日常の風景の中から、表に出てこない要素を読み取る力。
機械的な計算では補えない、人間ならではの感性で文脈や背景にまで意識を向けること。変化に抵抗するのではなく、自ら問いを立てて言葉にし、建設的に対話すること。
そこには、単なる情報処理ではなく、主体的な思考が存在していて、社会や組織を動かしていく原動力になるのかもしれませんね。AIやテクノロジーの進化は、自分たちの役割を改めて問い直す機会になっていると感じる今日この頃でした。
シンギュラリティがどんな未来をもたらすのか楽しみで、あと300年ぐらいは見ていたい。
死んでる場合じゃないと思いながら生きてます。早くも真夏日になりつつありますが、体調に気を付けて4Qも走り抜けましょう!